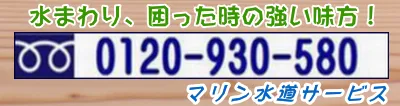水道用語リスト:和式トイレ

収録水道用語一覧
和式トイレ
日本で一般的に使われているトイレの一種であり日本式便所とも呼ばれます。和式トイレは、洋式トイレとは異なる設計と特徴を持っています。以下で和式トイレの特徴や構造に関する基本的な情報です。
●座位と姿勢
和式トイレでは、座るのではなく、しゃがむ姿勢を取ります。日本では、伝統的にしゃがむ姿勢が一般的であり和式トイレが適しています。
●構造
和式トイレは、通常、床に取り付けられた陶器製の便器(便槽)と便器の下に埋設された排泄物を受ける排泄槽からなります。洋式トイレのような水箱や水流はなく手動で水を流す方式が一般的です。
●水流と洗浄
伝統的な和式トイレでは、洗浄機能は付いておらず、流し方や洗浄は水を手動で使います。ただし、近年では一部の和式トイレには、洗浄機能やウォシュレット(おしりを洗浄する機能)が搭載されたモデルもあります。
●使用方法
和式トイレを使用する際は、便器の上に立ち両足で便器の両側のフットプレート(脚立)に立ってしゃがむ姿勢をとります。手すりがついていることがあるのでつかまって安定感を得ることができます。
●洋式和式折衷トイレ
最近では、座位は洋式トイレのようになっているが便槽は和式の構造であるいわゆる洋式和式折衷トイレも普及しています。
和式トイレは日本独自の文化や習慣に根ざしたものであり日本では一般的に広く使用されています。ただし、近年では洋式トイレの普及も進んでおり洋式トイレも一般的に利用されるようになっています。
和式トイレの構造について
和式トイレの構造は、日本独自の伝統的な様式を保ちながらも衛生的な排水を実現する設計が施されており床面に設けられた陶器製またはステンレス製の便器はくぼみを持ち人がまたがってしゃがむ姿勢で使用することを前提としているため腰をかける必要がなく接触部分が少ないことから公衆衛生の面で優れているとされる。便器の前部には排便を確実に受け止めるための隆起があり、そこから後方へとゆるやかな傾斜が設けられており排泄物は自然な重力に従って水封部へと流れ込む構造となっている。水封部はトラップ構造となっており一定量の水が常に保持されていることで、下水管からの悪臭や害虫の侵入を防ぐ役割を果たす。また、水の供給方式には二つの主要なタイプがあり、ひとつは水洗タンク方式でレバーを操作するとタンク内の水が一気に放出され、重力により排泄物を流す仕組みであり、もう一つは直接水道管から水が供給されるフラッシュバルブ式で、水勢を利用して瞬時に便器内を洗い流す方式となっている。
和式トイレの排水は通常床下に設置された排水管に接続され、この接続部分には防臭パッキンや水封装置が設けられ室内環境の清潔さを維持する工夫がなされている。多くの和式トイレは床の清掃性を高めるため、床面と便器の継ぎ目に段差がないように設置されている。また、タイル張りなどの防水性・耐久性に優れた素材が使用されることが多い。近年では、水の使用量を抑える節水型の設計や、感染症対策としてタッチレスで水を流せる自動洗浄システムを備えたものも登場しており伝統的な構造を維持しながらも機能性の向上が図られている。和式トイレは、しゃがむ姿勢が腹圧をかけやすく排便をスムーズにするという健康上の利点もあるとされるが高齢者や身体の不自由な人にとっては使いにくい側面があるためバリアフリー化が進む現代では洋式トイレへの改修も進んでいるが和式トイレ特有の構造は簡素で故障が少なく清掃しやすく維持管理が容易である点から、学校や公園、公共施設などの多目的な場所で今なお採用されるケースが多い。また、地震などの災害時においても復旧の早さや配管の単純さが評価されるなど実用性の高い設備として位置づけられている。